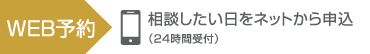最近、ジェローム・グループマン(ハーバード大医学部教授)の著書「医者は現場でどう考えるか」を読んだ。
最近の若手医師は、自分で考えることを放棄し、マニュアル化された判定システムに基づいて診断する傾向が強く、また、患者の話をじっくり聞いたり、鋭い観察をする能力にやや欠けるのではないかと感じたことが執筆の動機であるそうだが、内容は、「なぜ、どういうプロセスで、医師は診断を誤ることがあるのか」という視点から医師のあるべき姿を問うものである。
たとえば、「はじめに 虚心に患者と向き合う」の章では次のような事例が紹介される。
ある女性患者は、15年間食べては嘔吐することを繰り返し、多くの医師から過敏性腸症候群と診断されてきた。ある時、彼女は「どうせ同じような診断だろう」と半ば諦め気分で、ある医師の診察を受けたが、同医師は、彼女が持参した15年間のカルテを脇に置き、発症からこれまでの経緯を詳細に聞き取り、別の原因を疑って検査を行い、ついに特定の物質に反応する自己免疫疾患であることをつきとめる。先入観にとらわれず、虚心に患者と向き合った同医師の態度がそ の結果を導いたというのである。
それ以外にも、多くの医師にインタビューをして、あるべき医療を実現するための様々な教訓を導き出し、「おわりに 患者の物語をききとる」の章で終わる。
病名や薬剤名が飛び交い、内容は決して平易とは言えない。しかし、この著書を読むと、月並みではあるが、医師も弁護士も、相手(患者または依頼者)と充分なコミュニケーションをとり、相手に真摯に向き合って信頼関係を築いていくことが極めて重要であるということを再認識する。さらに言えば、それは人が社会生活を送っていくうえで必要なことでもある。
自省を迫る一冊である。