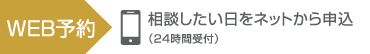1 遺言は、自らの相続に関する生前の意思を表明する重要な制度である。
遺言が有効であれば、その内容に従った処理がなされ、あとは「遺留分」が問題になるだけであるが、「遺留分」は「法定相続分」より少ないから、遺言によって十分な利益を得られない法定相続人が遺言の有効性を争う場合が生じる。
比較的多いのは、遺言作成時に遺言能力があったかどうかという争いだが、それ以外に、遺言の解釈が問題になることもある。
2 遺言作成時、Xに、A、Bという2人の子がいる場合を考えてみよう。Aにはaという子(Xの孫)がいる。
Xは、「すべての財産をAに相続させる」という遺言を作成したが、その後、Aが先に亡くなり、次いで、Xが亡くなった。aはAの代襲相続人としてXの法定相続人になるが、上記遺言によって、すべての財産を取得できるかが問題になった。
最高裁平成23年2月22日判決は、Aが先に亡くなった場合にはaに相続させる意思をXが有していたという特段の事情がない限り、上記遺言は無効であると判断した。遺言によって利益を得る者は生存していなければならないということである。
3 今回紹介するのはその変型で、簡略化すると次のような事案である。
遺言作成時、Xには、A、B、Cという3人の子がいた。
Xには複数の財産があり、Xは、財産ごとに、AからCの3人の子に割り振って相続させる旨の遺言書を作成した。そのため、遺言書は複数の条項にわたっていた。
その後、Aが先に亡くなり、次いでXが亡くなった。
Aが先に亡くなっているので、亡Aに相続させる旨の条項が無効であることは上記最高裁判決から導くことができるが、それを超えて、遺言全体が無効になるのかが争いになった。
冒頭の東京地裁判決は、遺言全体は無効にならず、亡Aに関する部分以外の条項は有効と判断した。財産ごとに検討がなされており、ある財産をある子に相続させる意思が明確で、亡Aに関する条項が無効ならすべてを無効にしなければならないような事情はないことを理由とする。
4 問題になったのは、遺言の解釈である。
本件であれば、遺産を取得させたい相手が先に亡くなった場合はどうするかを定めた「予備的遺言」をしておけばよかったということになる。
遺言は公正証書遺言が望ましいが、できる限り将来に紛争が生じないよう、事前に遺言内容を十分検討することが大切である。