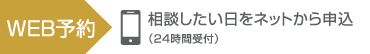映画「ペコロスの母に会いに行く」を見ました。友人から、まだ出版さればばかりのころに原作の漫画本をいただき、その着想の豊かさとお母さんをみつめる視線の優しさにファンになり、映画の完成をかなり前から楽しみにしていました。こういう場合、えてして期待が膨らみ過ぎてしまうものですが、とてもいい作品になっていました。
原作の、認知症ということを温かくとらえ、過去の記憶の中に生きる母の人生を、長じてもう一度一緒に辿ってみるという視点を、ユーモラスさをそのままに生き生きと描いています。それだけでも、この優れた原作の映像化としては十分に成功したと思います。
ところが、森崎東監督は、さらに、折々に、長崎の被爆の歴史や戦後の長崎の庶民暮らしを透かして描き、あるいは、認知症を受け入れがたいもう一人の親子(竹中直人の演技が秀逸)の変化を描くことで、さらに映像作品としての深みを増すことになったように感じました。 私も、普段、1~2か月に1度、施設オンブズマンとして通っている特別養護老人ホームで、様々な人生を送ってこられた認知症をもつ方々が、生き生きと話してくださる戦前、戦中、戦後の苦労話に、往時を想像しながら耳を傾けることがありますが、それをこのような形で昇華された原作と映像に改めて感銘を受けました。
ちょうど同じ時期に、NHKスペシャルで、認知症の母との介護の記録映像や都会で孤立する高齢者を取り上げた特集を見ましたが、その視点のあまりの違いにいろんなことを考えさせられもしました(そのことは、いずれまた書きたいと思います)。
惜しむらくは、「ペコロスの母」は過去に生きているだけではなく、今を、息子との今を、しっかりと感じ取りながら、彼女らしく今を生きているんだ、という視点が加われば、と思ったのは、ちょっと贅沢な望みなのかもしれません。