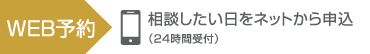遺言は、弁護士がしばしば取り扱う分野である。
最近、遺言を巡って興味深い判決が出たので紹介する。
【自筆証書遺言の効力が問題となったケース】
東京地裁・平成28年3月30日判決である。
民法968条1項は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」と定めている。
遺言書の日付は平成19年12月21日とされていたところ、判決は、実際に作成されたのは平成20年4月23日以降であり、意図的に日付を遡らせたと認定した上で、このような場合、形式的に日付の記載があっても自筆証書遺言は無効と判断した(控訴)。
日付は、その当時遺言することができる状態にあったかどうか、複数の遺言がある場合にどちらが優先するかを決める基準になる。意図的に日付を遡らせることを法は認めていないということである。
【公正証書遺言が望ましい】
自筆証書遺言は、「本人の自筆ではない」、「遺言する能力はなかった」など、後に効力を争われることが多い。また、相続開始後、家庭裁判所で検認手続きを受けなければならないという面倒もある。
したがって、これから遺言を作成するという場合、公証人が作成する「公正証書遺言」によることが望ましい。
【公正証書遺言の効力が問題となったケース】
とはいえ、公正証書遺言であっても、ときに効力が争われることがある。東京地裁平成28年8月25日判決がそれである。
事案を簡略化すると次のとおりである(わかりやすくするために修正を加えている)。
遺言者(A)は二度結婚。最初の夫との間に子(X)がおり、夫と死別。再婚相手は前夫の弟であり、同夫との間にも子(Y)がいる。AはY夫婦と同居生活を送った後、施設に入った。A(90歳)は、平成19年、Aは「すべての財産をXに相続させる」旨の公正証書遺言を作った。
そのことを知ったYはAに働きかけ、A(92歳)は、平成21年、「すべての財産をYに相続させる」旨の公正証書遺言を作った。
遺言は最新のものが優先する。そこで、XはYを相手に平成21年遺言は無効であるとして裁判を起こした。母は同じで、父親は兄弟同士。ドラマになりそうなケースである。
平成21年遺言当時、Aはアルツハイマー型認知症と診断されていた。しばしば活用される認知機能テスト(改訂版長谷川式簡易スケール)では30点満点で9点。数値上はかなり高度の認知症が疑われた。
公正証書遺言の作成には弁護士が関与し、遺言能力が問題となり得ることを想定してか、事前に、別途、医師の診断書を取り付けている。また、公証人による意思確認もなされている。
それでも、判決は、平成21年遺言当時のAとYとの会話の録音その他の証拠に基づき、Aには遺言能力がなかったから同遺言は無効と判断した(控訴)。
【遺言の作成は様々な角度から検討を】
相当高齢になってから遺言書を作成することはしばしばあり、その場合、「遺言能力」が問題となりうるが、認知症が進んでいたとしても、直ちに遺言能力がないとされるわけではない。
裁判実務においても、①遺言当時に精神上の障害があるか、あるならば、その内容、程度はいかほどか(認知機能テストの結果は、その判断のための一つの資料にとどまる)、②遺言の内容が複雑かどうか、③遺言をするに至った動機・理由、④遺言者と利益を得る相続人との人的関係や交際状況等の様々な事情を総合的に考慮して、遺言能力を判断するという枠組みが定着している。
したがって、認知症が進んでいるからと言ってあきらめるのではなく、将来争われるかもしれないという一定のリスクがあることを理解しつつ、可能な限り遺言の作成を追求するという姿勢が求められる。