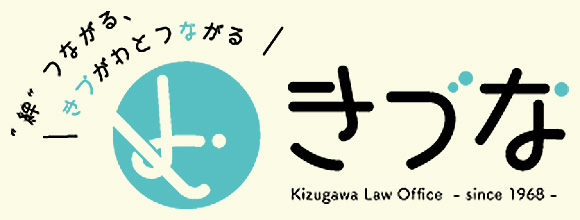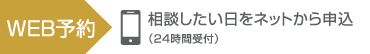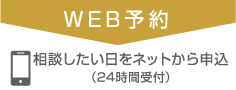さる3月4日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案が閣議決定されて、国会に提出されました。
建物と居住者の「2つの老い」に対処することが改正のねらいですが、見過ごすことができない問題点が含まれています。
1 賃貸借終了請求権~分譲貸しの賃借人は問答無用で立退き!
1つは、分譲貸しの賃借人に対して、昨年3月15日の「ことのはぐさ」でも書きましたが、建替え決議があったときは、賃貸人である専有部分の区分所有者はもちろん、建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者も含めて、専有部分の賃借人に対して、賃貸借の終了を請求することができる権利を付与し、請求がなされたときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から6か月を経過することによって終了することとしています。その際、賃貸人は、いわゆる用対連基準に従って算出される通損補償と同水準の額の金銭を「賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金」として支払わなければならないとしています。賃貸人以外の者で賃貸借終了請求をした者は、賃貸人と連帯して、補償金を弁済する責任を負うとされます(改正法案64条の2)。
しかし、マンションの建替え決議がなされたときは、賃貸借契約の解約や更新拒絶の「正当の事由」(借地借家法28条)の一つの考慮要素にすぎず、建替え決議がなされたからといって、ただちに「正当の事由」が認められるものではありません。また、「正当の事由」の不備を補完するものとして考慮されるいわゆる立退料についても、用対連基準で算定するという機械的な判断をしているものではありません。なぜ、マンションの建替え決議がなされた場合にのみ、このような機械的、一律な判断で、賃借人を立ち退かせることができる例外を認めるのか、理解に苦しみます。借地借家法による賃借人の住み続ける権利を骨抜きにするものであり、「正当の事由」の存否の判断にも悪影響をもたらすことが懸念されます。このような例外を設ける必要はなく、借地借家法によって対処されるべきであって、賃借権終了請求権は削除されなければなりません。
2 共用部分等に係る請求権の行使の円滑化~共用部分の「円滑」に補修ができない?
もう1つは、共用部分等に係る請求権の行使の円滑化を図るとして、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求・受領につき請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であった者)を代理すると定めた点(改正法案26条)です。
しかし、共用部分の補修請求権に関して、東京地裁平成28年7月29日判決は、区分所有者に分割して帰属するから、区分所有権が譲渡されても新所有者は当然に承継される者ではなく、分譲時と請求時に区分所有者が異なる場合には、旧区分所有者から債権譲渡を受けなければならないとの判断を示しました。したがって、管理者が請求権の行使を代理する権限が与えられただけでは、旧区分所有者に請求権が帰属したままになるので、管理者が勝訴しても、ただちに、旧区分所有者が有している請求権に相当する賠償額を受け取ることはできません。
また、改正法案26条は、ただし書きで、別段の意思表示をした旧区分所有者には適用しないとされていますので、旧区分所有者が、管理者への代理行使を認めず、自ら請求することになれば、区分所有者全員のために管理者に統一的な行使ができなくなってしまいます。
これでは、「2つの老い」に対処するどころではありません。真に、共用部分等に係る請求権の行使の円滑化を図ろうとした趣旨の実現とするのであれば、共用部分等に係る請求権は、区分所有権の譲渡にともなって当然に承継されることとすること、区分所有者の個別の行使を認めず、管理者による一元的な行使とすること等の修正が必要です。
この問題点については、欠陥住宅全国ネットがパンフレットでわかりやすく伝えており、また、日経クロステックの2月25日の記事でも、詳しく取り上げられています。
3 国会審議では問題点を洗い出し、必要な修正を!
ほかにも、マンションの再開発を優先する観点から、決議要件の緩和など、デベロッパーのための改正で、居住者の権利の保障を後回しにしているのではないかと思われるものもあります。
国会での審議では、徹底的に問題点を洗い出して、必要な修正がなされることを期待します。