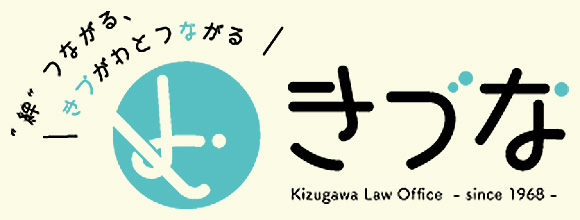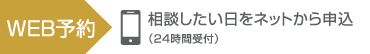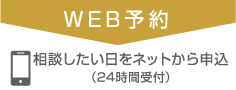特別寄与料とは何か?
特別寄与料請求制度(民法1050条)は、平成30年の民法改正により、新たに設けられました。
従来、相続について、相続人が被相続人の財産の維持、増加に寄与した場合は、「寄与分」として、その貢献が評価されてきました。今回の民法改正により、新たに、相続人以外の人が寄与した場合に、相続人に対して、その寄与に応じて、寄与料を請求することができるようになりました。
新設された民法1050条は、相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした場合に、相続人に対し、寄与に応じた特別寄与料の支払いを請求できるとしています。
従来、相続人に限り認められていた寄与に関する主張を、相続人以外の親族にも認める点に違いがあります。
相続人ではない親族の貢献についても、法的に評価しようという趣旨です。例えば、両親と息子夫婦が同居していたような場合、息子の妻が、夫の両親の介護をすることがあります。その場合、親が亡くなった場合、息子の妻は相続人ではありませんので、寄与分を主張できません。ただ、このような場合も、相続人である息子とその妻の貢献を一体として評価して、相続人である息子の寄与分が評価されてきました。その意味で、息子の妻の貢献も寄与分の計算において評価されてきました。しかし、この場合でも、妻は、相続人ではないため、独自にその貢献を妻の権利として評価されることはありませんでした。
このように、相続人ではないけれども、被相続人に対する貢献がされている場合に、それを評価する道を開いたのが、この特別寄与料制度です。
ただ、従来の寄与分の制度を一歩拡張した関係から、その適用には、一定の制限が設けられました。
第1に、特別寄与料請求ができる人は、被相続人の親族(6親等内の血族、2親等内の姻族)であることが要件になります。被相続人の親友が貢献をしたような場合は、親族ではないため、特別寄与料の請求はできません。
第2に、請求について、短期間の期間制限が設けられました。
特別寄与料の請求については、当事者間で協議がされることになり、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停、審判がされることが予定されています。しかし、請求には期間制限があり、①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月を経過したとき、又は、②相続の開始の時から1年を経過したときは、請求できません。
ですから、子どもや配偶者に対する請求では、被相続人が亡くなってから1年が経過すれば、請求できなくなります。
最高裁判決の事案の概要
このような特別寄与料の支払いを、遺留分侵害額請求をした相続人に対して請求できるかという問題について、2023年10月26日、最高裁の判決が下されました。
本件は、亡甲の親族Xが、甲の相続人の1人であるYに対して、特別寄与料の支払いを求めた事案です。
甲の相続人は、甲の子どもである乙及びYです。Xは乙の妻にあたります。甲は、生前、全財産を乙に相続させる旨の遺言をしていました。裁判では、この遺言は、甲の相続分を100と指定し、Yの相続分を0と指定する趣旨を含むと認定されたようです。
甲は令和2年6月に亡くなり、令和3年3月、Yは、甲に対し、遺留分侵害額請求をしました。
これに対し、甲の妻であるXが甲の兄弟であるYに対して、特別寄与料の請求をしたのが、本件です。
最高裁の判断
最高裁は、「遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である」として、XのYに対する特別寄与料の請求を認めませんでした。
解説
特別寄与料の請求を受ける相続人が数人ある場合には、特別寄与料は、民法900条から902条の規定により算出した相続分に応じた額を負担するとされています。
そして、902条は、被相続人は、遺言相続分を定めることができる旨の規定をしており、この規定からすれば、本件は、遺言書により、相続分を甲が100、Yは0としていますので、XはYに対して特別寄与料の請求ができないことになります。
他方、本件の場合は、Yが遺留分侵害額の請求をしており、その結果、Yは遺留分に相当する遺産の1/4の請求をすることになります。そこで、特別寄与料の1/4をYが負担することになるのではないかとの主張があり得ます。
しかし、遺留分侵害額請求がされた場合の各相続人の負担については、民法1050条は明文の定めをしておらず、これが、本件で問題となりました。最高裁は、遺言により相続分が0と指定された相続人は、遺留分侵害額請求をしても、特別寄与分を負担しないと判断しました。
ちなみに、遺留分侵害額請求権にも期間制限があり、相続開始及び遺留分を侵害する贈与等を知ったときから1年以内、または、相続開始から10年以内とされています(民法1048条)。そして、特別寄与料の期間制限が、前述の通り、相続開始及び相続人を知ってから6ヶ月、又は、相続開始から1年ですので、遺留分請求の制限期間より短くなることがほとんどとなります。そして、遺留分請求が特別寄与料の期間制限の経過後にされた場合には、特別寄与請求の期間制限の関係から、遺留分請求をした相続人は特別寄与料の負担をしないことになります。
最高裁の判例の場合は、遺留分請求がされる時期が、特別寄与料請求の期限の前後を問わず、相続分を0と指定された遺留分請求者は特別寄与料の負担をしないことになります。
逆に言うと、遺留分請求の時期により、特別寄与料を負担するか否かが決まるという事態は、なくなることになります。
それでは、本件のように相続人の妻が、被相続人の財産の維持、増加に貢献した場合、遺留分侵害額請求に対して、夫の貢献と一体化して寄与分を主張する道はあるでしょうか?
結論からいうと、そもそも、遺留分侵害額請求に対して、寄与分を主張して拒否することはできません。
遺留分を計算する際に、「遺贈」や「贈与」(特別受益)は加えて計算するのだから、逆に「寄与分」は差し引くべきではないかとも思われます。しかし、遺留分の計算の際に「寄与分」を理由として遺留分侵害額請求を拒否できるとする条文は、民法上存在しません。
従って、本件のように遺留分侵害額請求がされている場合、「寄与分」や「特別寄与料」を主張することは、できないことになります。