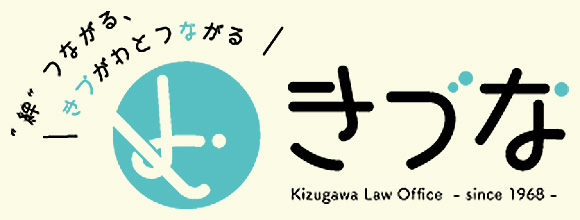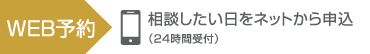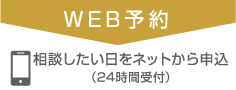現在は、夫婦が離婚した場合、未成年の子はどちらかの親権に服することになっています(単独親権)。ところが、令和6年5月から2年以内に、単独親権だけでなく共同親権も認められる内容の改正法が施行されることになりました。施行日はまだ決まっていませんが、施行後は共同親権も認められることになります。
単独親権のみの制度から共同親権も可能とする制度に変えるにあたって、賛成派と反対派で活発な意見交換がなされました。反対派の根幹にある感覚は、「関係がうまくいかなくなって離婚することになった夫婦なのに、子のことについて本当に協力できるだろうか、意見が食い違う場合に適切に対処できるだろうか、夫婦間の力関係のゆがみを子に持ち込むことになったら子どもの利益にはならないではないか。実際に、子の養育に不適切な親もいるではないか。」というものでした。賛成派は、「離婚後も子のことに積極的に関わり合いたい親は多い。適切に共同親権を行使できる元夫婦も多い。離婚したからといって当然にどちらかが親権を失うのは夫婦関係と親子関係を混同するものでそもそも不合理。」というものでした。
そこで改正法にはこれらの懸念に対する対応も盛り込まれました。
(1)まず、協議離婚の際は、父母の協議によって共同親権か、一方の単独親権かを決めることができます。協議がととのわない場合は、家庭裁判所が共同親権か一方の単独親権かを指定します。
(2)しかし、共同親権とすることによって子の利益を害する場合には、単独親権としなければなりません。例えば、子への虐待のおそれがある場合や、配偶者に対するDV(家庭内暴力)の恐れがある場合などです。
(3)なお、一旦単独親権と定めた場合であっても共同親権に変更する申立てをすることができますし、共同親権から単独親権への変更や、単独親権者の変更申立てをすることもできます。この場合は、合意が適正かどうかという観点から協議の経過を考慮することになりました。
(4)ただし、共同親権となった場合であっても、「子の利益のために急迫の事情があるとき」(例えば緊急の場合の医療、DVや虐待から逃れるための転居など)や、「看護および教育に関する日常の行為」(子の身の回りの世話、習い事の選択、一般的な医療やワクチン接種など)については、単独で親権を行使することができます。
(5)そして、これらの制度が適切に運用されるために、「婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して追う責務があること」および「親権が子の利益のために行使されなければならないものであること」が法律上明確化されました。
いろいろな議論を経て改正された法律ですが、大切なことは、親のための共同親権として運用されるのではなく、子のための親としての共同親権を実現できるような運用がされるように関わっていくこと、親としての自分たちも「子のための親」であることを忘れないようにすることだと思います。